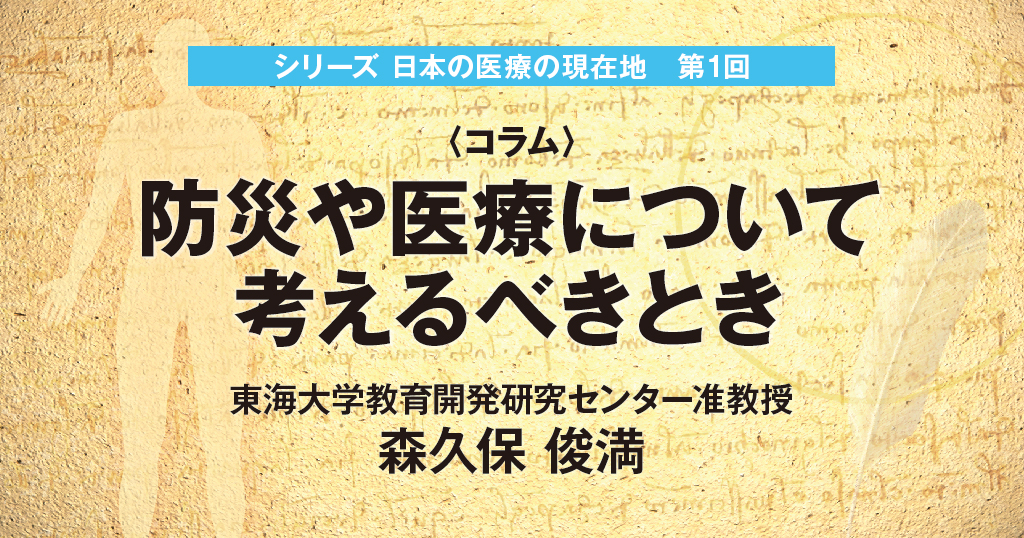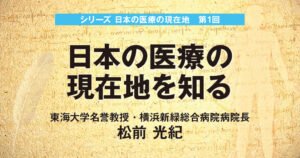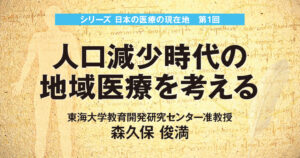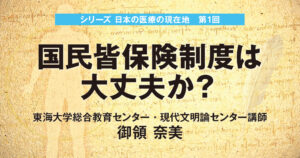ここ数年、大学で新入生の授業を何クラスか担当している。不安と期待に胸を膨らませたフレッシュな若者たちは、新しいキャンパスに慣れるのに必死であり、たいへんな集中力でものごとを吸収していく。二ヵ月もすると様子が分かってきてかなり落ち着いてくるが、それまではクラス内の緊張感がひしひしと伝わってくる。
私の授業では「地域」について考えている。地域学習にはいろいろな切り口が考えられるが、この新入生のスタートラインでは、「防災と医療」をテーマに授業を進めている。学生たちの中には地元出身者もいるが、大学入学のために引っ越しをして、知らない地域で生活をはじめている人が大勢いる。
こうした時期に、四年間を無事すごすために必要な地域の情報を自分で集められるようにうながすのである。大雨や地震、津波や水害などを念頭に、ハザードマップで通学経路や避難所情報を収集する。行政が取り組む防災対策や消防システムなども紹介する。
いざというときにどう対処し行動すればよいかという学習は、学生たちにとって取り組みやすいように思う。授業課題としては自分の住んでいる地域の調べ学習を設定するだけなのだが、自発的に「ふるさとの家族が住む地域も調べよう」「おじいちゃん、おばあちゃんの家は大丈夫かな……」という動きがでてくる。
また、「いざというときには家族と連絡をとりあえるようルールを決めよう」「防災グッズや食料をアパートに備えておこう」という方向になる。六月には大雨、夏には台風などが懸念されるが、多くの学生たちが気象情報や災害情報に耳を傾けるようになってくれる。「遊びに行った先でも危険を回避する判断ができるようになっておきたい」「被災したときには一番体力のある自分たちが人を助ける役割を担わなければならない」といった考察につながっていく。
このようなすばらしい考え方がでてくるのは、もちろん学習成果のたまものだが、おそらくは入学して最初の春だからだと思う。慣れない環境に置かれたときに、対処のすべを知ろうとすることは非常に効果的なのだろう。すっかり慣れた秋にはまた違うアプローチが必要になるのだが、こうした若者の防災意識が育つことは大変重要であると思う。
いま日本では、南海トラフ地震や不安定な国際情勢が巻き起こす紛争の可能性など、有事が起きたときの対応が必要とされている。もちろん国民を守るための医療についても、もしものときのための備えが必要となる。いま防災対策や国民保護のための取り組みについて議論することは、とても大切だと言えるのではないだろうか。
このような取り組みについては、「慣れ」との闘いでもあると思う。住み慣れた地域で危機に対処する難しさをどう突破できるか、どんな避難行動がとれるのか、これは国民全員の課題といえるだろう。

もりくぼ・としみち 1995年立正大学大学院文学研究科修了。2000年東海大学入職。健康科学部准教授を経て現職。山野美容芸術短期大学客員教授。医療法人社団こうかん会理事。地域における医療‧福祉政策を中心として、研究‧教育に携わる。