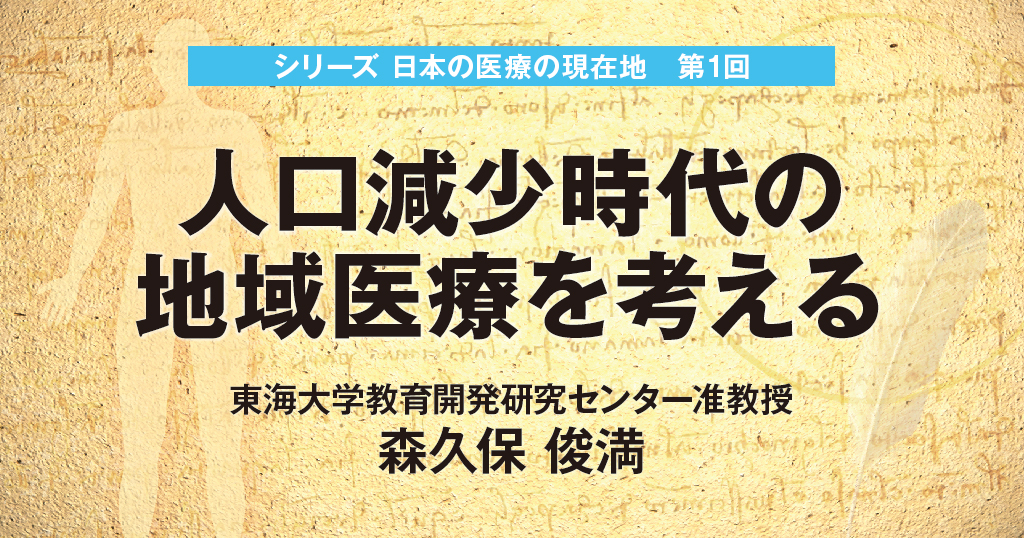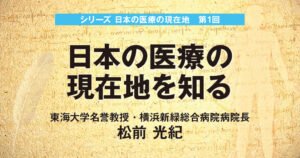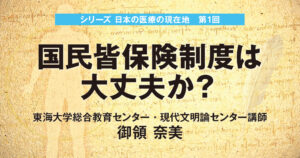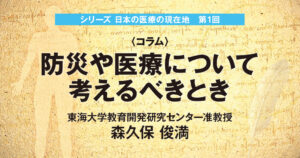少子高齢化が進んでいる日本では、2025年に国民の五人に一人が後期高齢者になるといわれ、今後、経済成長の低迷や地方の空洞化が進むと予想されている。それは医療についてもいえ、地域によって医療の格差が広がってしまう懸念がある。これからの医療はどうなるのか、格差を解消するための方法はあるのか、東海大学教育開発研究センターの森久保俊満さんに綴ってもらった。
病院をめぐる地域の動向
医師と医療法人が自由に開業できる日本においては、へき地など「医療密度」の低い地域に「公的病院」を建てて住民の不便を補う仕組みがあります。「公的病院」とは、病院「開設者」別に厚生労働省が定めた分類の一つであり、都道府県や市町村、「日赤」「済生会」「厚生連」「国保連」などが運営する病院のことです。
この公的病院は、開業医や医療法人の配置が少ない地域でも、住民が救急医療や専門医療にアクセスできるよう、地方自治体の医療政策等によって配置されています。公的な使命をもって誕生した歴史をもつ医療機関が多く、例えば「日赤」の設立は西南戦争の昔に遡り、「済生会」は明治天皇の御下賜金によって開設されています。
また、「厚生連」や「国保連」、地方行政が設置する病院は、国民皆保険を実現するために開設されたり、無医村やへき地の医療を担ったりするべく設立されてきました。令和五(2023)年度には、全国8122の医療機関のうち、7000弱が医療法人や個人開業医で、公的病院の数は1191となっています。多数は民間病院が占めていますが、公的病院の存在によって医療資源の偏在を回避してきた、というのが戦後の日本の姿といえるでしょう。
どうやら医療の偏在については、江戸時代からそのような問題があったらしく、徳川吉宗に献策した荻生徂徠の『政談』に、医師が都会に集まってしまうのでできる限り田舎に配置すべきという意見が述べられており、たいへん興味深いことです。現代の日本においては、これまで自由開業の病院と公的病院の組み合わせがうまく機能していました。
ところが、こうした調整も効かなくなるほどの状況が、いまの日本には起きています。それは何かというと、高齢化に続く人口減少の問題です。日本の人口は全国でみると、2008年の1億2800万人強をピークに減少に転じています。
直近の国政調査でみると、都道府県では東京都、政令指定都市では福岡市、さいたま市、大阪市、千葉市、川崎市以外、つまり一部の大都市以外はみな人口が減少しているのです。こうした人口減少は、自治体の税収減と患者数の減少をもたらしており、公的病院の多くが財政問題をかかえて縮小、再編、閉鎖の検討に入り、選挙の争点になっている自治体もあるのです。
高齢化と医療・介護問題
なぜそのようなことになってしまったのか、少し遡って高齢化の問題から検討してみましょう。
病院は、私たちがあまり意識しなければ、いつも変わらない姿で地域に存在しているように見えます。しかし十年、二十年、あるいは五十年、百年という単位で見ると、相当にその姿を変えていることに気づきます。さまざまな医療機関が患者のニーズに合わせてその機能を変化させてきており、最近の顕著な例としては、1970年代から顕在化し始めた高齢者医療の課題があります。
1973年から1982年までの間に実施された公費負担(税金)による「老人医療費無料化」を覚えている人が多いかもしれません。この政策は、当時まだ平均的な年金受給額が低かったこともあり、高齢者が安心して受診できる環境を整えたといえるのですが、高齢化社会の進展に伴って社会保険で賄う医療費への税金投入が増大し、本来在宅ケアや介護施設にゆだねるべき患者の入院期間の長期化をまねき、大きな課題となりました。
その後、高齢期の患者に対する治療の方法や病床機能のあり方、医療費の自己負担のあり方や家族ケア、介護サービスなどの課題が顕在化していきました。
初期に行われた改革は、1983年の「特例許可老人病棟」の制度でした。当時の日本は、結核などの感染症も克服し、高度経済成長を経て働き盛りの人口を多く有する豊かな社会を実現しつつある時期であり、病院の多くが「急性期」病棟で構成されていました。
リハビリの必要な患者や回復の望めないような患者のための病棟というものが広く位置づく状況にはなく、この時期に急速な人口高齢化を背景として高齢者に特化した病床機能が登場したのです。また1982年の「老人保健法」は、老人医療費の無料化を廃止しましたが、急性期病床における長期入院患者を減らすことを目標に、老人病棟の制度化とともにリハビリや介護に結びつけるための「老人保健施設」(今日の介護老人保健施設)を誕生させるなど、高齢者の医療・介護ニーズに応えるための大きな改革への一歩を踏み出しました。
さらに医療領域の改革に加えて、1980年代から90年代にかけては、戦前の「養老院」にルーツをもち、社会福祉制度で運営されている「特別養護老人ホーム」が一般に認識されるようになりました。この特別養護老人ホームを核とした「入所サービス」と「在宅サービス」が急成長し、退院後の介護やリハビリを支えるようになったのです。
2000年以降、高齢者福祉制度の多くが介護保険で運営されるようになり、医療との結びつきを一層強化して、病院は病院の機能を発揮し、介護ニーズには介護サービスが利用できるよう取り組みが進められました。
病床機能の変化と医療・介護の再編
民間組織である医療法人は、地域の医療ニーズにあわせてその機能を変化させるよう努力してきました。重篤な患者の集中的な治療を行う「急性期」「亜急性期」病床機能が多かったかつての病院の多くが、「回復期」や「慢性期」の病床機能を強化してより高齢者の病態にあった医療サービスを提供できるよう変化をとげています。
さらに、病院の同一経営母体に介護保険サービスを一体化させることにより、患者の発病期から慢性期、在宅ケアまでシームレスに対応できる体制を整えている医療法人もあります。このように地域の医療ニーズを吸収してきた民間医療法人が高齢者医療・介護問題に大きな力を発揮してきており、日本の医療が、民を中心として公が補完する体制をとることによって人口構造の変化に対応し得ているといえます。
しかし、急速な人口減少の進む現在、人口密度の低い地域においては、医療も介護もその存続が大変難しい状況になっています。これまで、公的病院の存在意義はこうした状況で発揮されてきているのですが、このような地域の多くの自治体では、税収が減少する中で病院運営の財政負担が大きくなりやすいのです。
市町村立病院の人材確保や設備の維持を考えると、人口の少ない市町村単独で病院を運営することは大変困難と考えられます。加えて一人暮らしや老夫婦世帯の在宅ケアを担う介護保険サービスはほぼ民間組織で担われているため、働く世代が少なく介護人材の確保が難しい地域への事業展開は容易ではありません。
今日、こうした状況に対応するべく、公的病院の見直しが図られるケースが全国的に増えています。早い段階で問題に対処した病院の一つが、2008年に公立病院の再編を実現した日本海総合病院です。同病院は酒田市にある山形県立病院と酒田市立病院を再編し、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構を発足させて両病院の機能再編を実施しましたが、その結果、病床をスリム化し救急から高齢者医療・介護を包含する病院に生まれ変わることができました。
この再編・統合は大変注目され、その後の公立病院改革の参考とされています。しかし病院の統合・再編は容易ではなく、今日、各地の自治体で病院の存続や再編をめぐる議論が続けられているのです。
地域によっては、市立病院を拡充するかわりに県全域をカバーする厚生連の病院を充実させ、へき地や離島に赴任可能な人材を確保するような対応が取られているケースもあります。厚生連以外に、全国にある日赤や済生会も「公的病院」として機能していますが、より柔軟に地域のニーズに対応しながら、医療法人と同様、その傘下に介護サービスを一体化させることも進めています。
また、改革に時間を要する公立病院を独立行政法人化することにより地域の民間病院と連携しやすくしたり、急性期から慢性期までの連続性を確保したりする方法を生み出したところもあります。
このように医療の戦後のあゆみを見ると、人口増加に追いつくように急性期病床を増やし、つづいて急増する高齢者の医療・介護ニーズに対応する病床や施設を増やしてきました。
しかしこの間、人口減少にともなう医療ニーズの変化にはなかなか対応しきれていなかった面があるのではないでしょうか。産科や小児科が地域から消えてしまう状況や、救急医療の網を広大な面積を持つ地域に展開すること、がん等に対応する高度専門医療の充実を図ることなどは、「医療密度」の低い地域にとって継続的な課題となってきたと考えられます。
病院と患者の需給バランスを図ることが非常に難しく、救急医の数が少なく患者の受け入れが難しい地域、産科医がいない地域、近くの病院が廃院となり通院困難な地域、せっかくの病院設備がありながら人材確保ができない病院の問題などが全国に散見されます。
これまで、官民の調和により人口集中地域では医療密度を高く保ち、過疎化が進む地域では公的病院の配置によって必要な医療を提供できるように図ってきましたが、今後は患者数や出生数がさらに減少し、医療・介護資源の配置がますます困難となるでしょう。
医療の地域格差をなくすために必要なこととは?
こうした課題はどのように対処されうるのでしょうか。一つには、今後もますます医療の「連携」を強化していくことになるでしょう。1980年代に制度化された「老人病棟」以降、1990年代に入ると「特定機能病院」や「療養型病床群」など病床機能の分化が始まり、90年代後半には「地域医療支援病院」が登場して、「病診連携」によって地域医療をバックアップする取り組みが始まりました。
もう一つは、病院運営をより広域で考えることです。2008年の日本海総合病院のように、病院の再編や統合が成功したり、機能の違う病院間の「病病連携」が検討されたりするようになっており、高度な専門性をそなえた病院を運営するためには人材や設備を集中していくことが必要となっています。
地域の医療の方向性を決める医療政策は都道府県が担っており、厚労省の指導のもとで「保健医療計画」を六年ごとに見直しながら医療資源をなるべく偏在のないよう配置してきました。
行政の管轄区域に医療圏域を定めて、管轄内のどの地域においても「5疾病」(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)に対応できるよう、また「6事業」(救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新興感染症等)が不足なく提供されることをめざしており、脳卒中や心血管疾患の救命率や予後の改善、地域から高度専門医療への「紹介」と地域への「逆紹介」など、患者が病態にあった医療を受けることができるよう積極的な地域連携が図られています。
このように最近の医療政策の方向性としては、「広域化」と「連携」がキーワードとなっているのです。人口動態を考慮すれば、公立病院の方向性をめぐり市民や県民が難しい判断をせまられる機会も出てくると思われますが、こうした課題に答えを出すためには、地域の将来を考える長期的な視野を養う必要性がありそうです。
先人たちのメッセージが解決のヒント
明治時代、湘南の海岸線は西洋医学の実践の場であり、やがて今日でいうヘルスツーリズムや移住の対象となるすばらしい保養地に成長していきました。その幕開けは大磯海岸です。
幕臣であり明治陸軍の軍医総監をつとめた松本良順は、長崎の出島に来ていたポンぺから、医学に位置づく「海水浴」の治療効果を学びました。大磯海岸に適性を見出した松本は地元と協力してすばらしい海水浴場を開いたのです。また、松本を慕って長崎に学び、内務省初代衛生局長となった長與專齋は、由比ガ浜に鎌倉海浜院を開きました。
さらに東京医学校に赴任したベルツは、源頼朝が愛でた葉山海岸の気候を絶賛。大船から鎌倉を経て逗子にいたる鉄道が開通した後は、これらの地域はすばらしい保養地となりました。また、茅ヶ崎の南湖院には医師高田畊安が東洋一のサナトリウムを開きました。このように、湘南海岸は、松本良順の海水浴場を嚆矢として保養と医療の海岸線へと成長したのです。背景には言うまでもなく結核を撲滅し克服するための熾烈な闘いがあったのです。
私たちが立ち向かう将来の課題は非常に大きいものですが、過去を遡ると大きな問題を乗り越えてきた先人たちの姿が見えてきます。縮小していく社会は前人未到の問題ではありますが、過去からのメッセージに耳を傾けながら取り組みを続けていけば、きっと難しい問題も解決していけるでしょう。

もりくぼ・としみち 1995年立正大学大学院文学研究科修了。2000年東海大学入職。健康科学部准教授を経て現職。山野美容芸術短期大学客員教授。医療法人社団こうかん会理事。地域における医療‧福祉政策を中心として、研究‧教育に携わる。