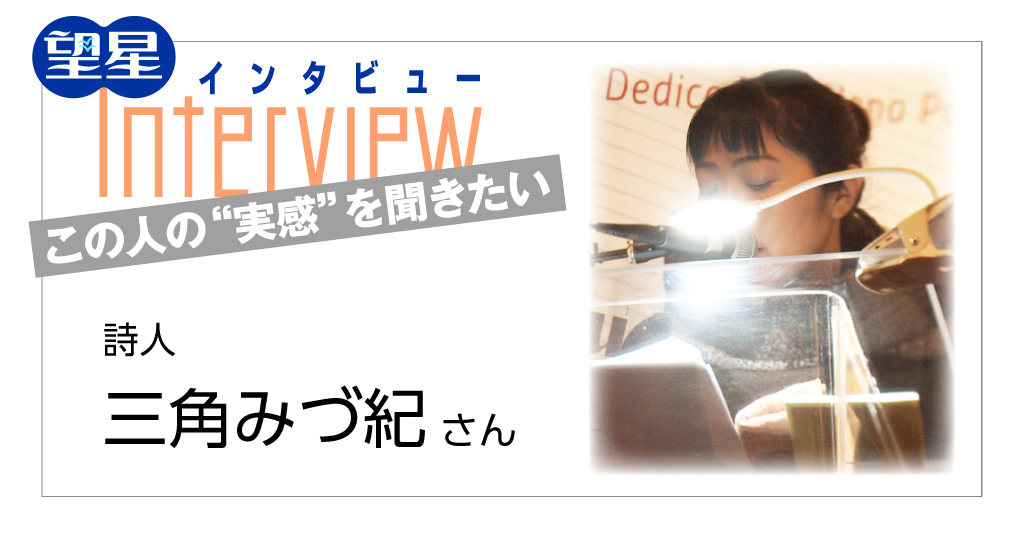詩がつなぐもの、詩から見えてくること
十二歳から詩作をはじめ、二十二歳で現代詩手帖賞を受賞したのを機に本格的な作家活動をスタートさせた詩人の三角みづ紀さんは、ある時期から旅をして詩やエッセイを書く機会が多くなり、いまでは毎年のように海外の詩のイベントに参加しているという。海の向こうで開かれる詩祭や文学祭で体感したことを中心に、三角さんのこれまでとこれからを聞いた。
(写真はすべて、三角さん提供)
書けば先につながる
――はじめに、三角さんが詩を書くようになった経緯を教えてください。
小学校の国語の授業で、五七五で自由に文章を考える時間があったんです。季語は気にしなくて良かったので、俳句ではないのですが。書けた人から黒板に書いていったんですが、特に勉強ができるタイプでもなかった私が、そのときは誰よりも早く、たくさん書けたんですね。もともと書くことも読むことも好きでしたが、このときに書く楽しさをあらためて知ったように思います。それで、卒業文集に将来の夢は作家と書きました。
中学生のころは写真を撮るのが好きになって、写真や映像関係の道に進むのもいいなと思い始めました。高校時代は音楽が好きで、デヴィッド・ボウイが出演するチャリティーイベントで流れていた短いドキュメンタリーに影響を受けて、戦場カメラマンになりたいと思った時期もありました。それは戦争の惨事のドキュメンタリーだったのですけれど、あまりに美しい映像で。こういう風に伝えるって大事なのではないか、と考えて。伝えるという点では、詩も似ていると思います。
大学では映像を学ぼうと東京造形大学造形学部視覚伝達学科に進んだのですが、一年目の冬に難病を発症してしまい、入院することに。みんなは学校でいろいろな経験をしているのに、私だけが前に進んでいない……そう感じられて、この時期はとても悔しかったです。そこで、病室でできることは何だろうと考え、思い当たったのが詩でした。それ以前から詩は書いていましたし、療養中でも自分のペースで書けますから、何か先につながる気がしたんです。
四ヵ月ほどの入院中、病院内のポストから『現代詩手帖』への投稿もはじめました。退院後、一年間の休学を経て、復学後も投稿は続けていました。投稿をはじめて二年目に第四十二回現代詩手帖賞を受賞。その際に編集部から「詩集を出しませんか?」というお話をいただいて刊行した第一詩集『オウバアキル』では、中原中也賞をいただきました。コンスタントに詩を発表するようになったのは、この二つの受賞の後です。依頼も増えてきて、徐々に詩以外の文章も書くようになりました。
毎年のように海外へ
――三角さんには『望星』2024年3月号で、メキシコのサンルイスポトシで開催された第十六回国際文学祭のレポートをご寄稿いただきました。サンルイスポトシの文学祭に限らず、詩や文学にまつわる海外のイベントには何度も参加されているそうですね。はじめて参加されたのはいつごろですか?
2012年ですが、それは大きなフェスティバルではなく、ハワイのあるカフェで開かれた詩の朗読イベントでした。
2011年に「しずおか連詩の会」に参加したとき、詩人の管啓次郎さんに旅のお話をいっぱいうかがう機会があって、私も旅をして文章を書いてみたいと思ったんですが、おすすめを聞いたらハワイだとおっしゃるんです。ハワイはいろいろな文化が混じっていて面白いと。それで、当時のツイッターで「ハワイエッセイの連載をさせてくれるところはありませんか?」という趣旨のつぶやきをしたところ、西日本新聞社で全五十回のお仕事をいただき、せっかく行くのだから何かイベントに参加したいといろいろ探して行きついたのがカフェでの朗読でした。私は英語があまり得意ではないので言葉の問題が心配でしたが、イベント担当の方のルーツが日本で、日本語が通じたので安心しました。
――カフェでは英語と日本語、どちらで朗読されたんですか?
日本語で朗読しました。お客さんはほとんど英語話者の方でしたが、ある高齢の女性が「言葉の意味はわからなかったけれど、声音がよかった」と言って腕輪をくださったのが、いまでも印象に残っています。旅先で、また朗読してみたいという気持ちになりました。
それ以来、毎年のように、海外で開かれる詩や文学のイベントへ行っています。ハワイの翌年には、欧州文化首都(※)の一環で、スロヴェニアのプトゥイという街に行きました。欧州文化首都に参加する日本人の支援をしている方から「スロヴェニアの詩人が会いたがっているので、行ってみませんか?」とご連絡をいただいたのがきっかけです。
※ 欧州の都市の活性化を目的とした文化事業。EUによって指定された開催都市では 1 年を通して多様な文化芸術プログラムが行われる
――いままでに訪れた国というと?
まだお話ししていない場所では、イタリア、リトアニア、セルビア、ハンガリー……日本の詩人の方が主催されたカナダでのイベントで朗読したこともあります。2024年の年末にはタイのバンコクの詩祭に行く予定ですが、アジアではタイが初めてです。
――毎年のようにイベントに参加されるのは、あるイベントに参加すると、そこで次のイベントに招待されたり、イベント関係者とのつながりができたりするからでしょうか。
そこは不思議で、なぜか毎年どなたかから連絡をいただいて、ありがたいことに参加できているんです。
私に会いたいと言ってスロヴェニアの詩祭に招聘してくれたのはアレッシュという詩人なんですが、アレッシュのように、こちらが知らない間に私を詩祭に推薦してくれている人がたまにいて、そういう方たちと実際にお会いして、新たなつながりをつくれるのは本当にうれしいです。スロヴェニアでの初対面以来、アレッシュとは交流が続いているのですが、メキシコでも偶然に再会することができて、とてもうれしかったです。

国によって違う詩と人々との関係
――今年(2024年)の7月には、コロンビアのメデジンで開催された第三十四回メデジン国際詩祭に参加されたそうですね。
そうですね。メデジンは、かつては麻薬カルテルの街で、麻薬王が亡くなった1990年代初頭から始まった詩祭なのだそうです。
世界各地から詩人が集まることで知られる詩祭でもあって、今回参加したのは80人ほど。初日に顔合わせのようなパーティがあり、翌日から数日はいろんなメンバーと四人一組になってバーや劇場、図書館などの会場を回って朗読をしました。最終日はすべての詩人が野外ステージで朗読したんですが、みんな時間を守らないので、最後は三時間くらいオーバーして、さすがに運営側の人が「時間を守ってください!」と怒っていました。なのに、その後も持ち時間をオーバーする人がいて、誰も時間を守ろうとしないんですよ(笑)。
私の朗読のときは、まずは日本語で、その後に現地のパートナーがスペイン語で朗読してくださいました。どんな詩を朗読するかは、参加する前に調べておいたその土地やフェスティバルのことをふまえて、この詩が聞いてくださる方にいちばん響きそうだなと思ったものを選びました。
――日本との違いを感じたり、カルチャーショックだったりしたことはありますか?
日本では詩がとっつきにくい存在だと思っている人がいっぱいいると思うんですが、そういう空気はメデジンではなかったですね。
メキシコのサンルイスポトシを訪れたときには、物価は安くても本は高くて、詩集を持っている人は少数派ではないかと思ったんですが、メデジンもおそらく同じで、それでも日本よりは詩が身近にある感じがしました。メキシコならオクタビオ・パス、コロンビアならガルシア=マルケスといった偉大な文学者がいることで、詩などの文学を身近に感じているのかもしれません。実際、人々が詩の朗読を楽しみにしている空気が伝わってきて、とてもうれしかったです。
サンルイスポトシとメデジン、どちらも詩に対する親しみは変わりなかったのですが、サンルイスポトシは文学と真摯に向き合う感じが強かったというか、文章としての詩に重きを置いているように感じた一方で、メデジンでの詩祭はロックフェスのようなテンションで、パフォーマンスを重視しているようでした。
たとえば、インドネシアの男性の詩人は、しゃべっているときはとても静かな印象でしたが、舞台ではメタルみたいな音楽を流してずっと叫んでいて、聴いている人たちが呆気に取られるくらい激しいステージでした。ほかにも、ボイスパフォーマンスをする人、弾き語りをする人など、詩人ごとに本当にいろんな表現をしていました。
日本では朗読詩人というものと紙媒体のみで詩を発表する詩人とがはっきり分かれていて、両者の間には距離があるように感じると、日本の詩人の友達と話すことがあるんですが、メデジンではそういうものがすべて一緒になっているような印象もありました。


――日本で詩の朗読を聞く機会は、学校の授業以外ではほとんどないように思います。韓国では、ドラマに詩が出てきたり、日常的に詩を諳んじることもあると聞いて、お隣の国でもずいぶん違うなと思ったことがあります。
去年の春にソウルで、日本語を勉強している方向けの詩のワークショップと、韓国の詩人との対談を行うイベントに参加しました。日韓国交正常化五十周年を機に始まった日韓若手文化人対話事業の一環で、私は詩人のオ・ウンさんという男性と対談しました。
日韓若手文化人対話事業に関わり、韓国では誰もが詩人と名乗れるわけではなく、新聞社主催の賞を取ったりしないと詩人とは名乗れないのだと教えてもらいました。そのことに受賞歴のある韓国の詩人たち自身も疑問がある方がいるようで、受賞歴がなくても自分がいいと思った書き手の詩集を出版できるようにしたりもしているようです。詩人と名乗れない人でも、詩を書いている人は案外多いのかもしれません。
K-POPのアイドルが好きな詩集をSNSで紹介もしています。韓国のドラマやアイドルが詩を取り上げるようになったのが先なのか、それ以前から詩がポピュラーなものだったのかはわからないのですが、とにかくいま韓国では若い人の間で詩が流行っているというか、「詩=かっこいい」という感覚がとても強いようで、書店の詩のコーナーの前に若い人たちがいっぱい集まっている光景が見られるそうです。
「読む」も「書く」も、淡々と
――日本でも朗読をされることがあると思うのですが、海外では読み方を変えているとか、逆に変えないようにしているとか、気をつけていることはありますか?
十年くらい前までは「人と違う朗読がしたい」という意識が強く、国内でも海外でも、そのためにはどうすればいいのかを考えるところがあったと思います。ですが最近は、聴く人の耳にちゃんと残るには、淡々と読むのがいちばんじゃないかなと思うようになりました。
今年の夏に、御徒町凧[おかちまち・かいと]さんなど数人の詩人と北海道の釧路で朗読したんですが、そのときに御徒町さんが「書いているときの声の大きさってどのくらい?」とおっしゃっていたんです。「書いているときの声の大きさって何だろう?」と思ったら、書いているときの文字の〝声〟の大きさのことで、朗読のときにはその〝声〟の大きさをそのまま再現するのがいちばんいいんじゃないかと。おそらく書いているときの気持ちも関係しているのだと思うのですが、この話はとてもしっくりきました。
私が淡々と読むようになったのも、書き方自体が淡々と書くようになったからではないかと思います。二十代のころは、自分が世界と闘っているような気持ちで詩を書いていました。その後、旅をして書くようになって、第五詩集以降は旅の詩集が多いのですが、旅をしているとどうしても無口になるので、詩自体も自然と寡黙になるというか、淡々とするんです。このころから、書く情報が少なくなったり、強い言葉を使わなくなったりした気がします。
――そもそも、朗読はお好きですか?
二十八歳のときに本格的に朗読を始めたんですが、それまでは朗読するなんて絶対に嫌でした。やっぱり、勝手に「ださい」みたいなイメージを持っていたんです。でも、いろいろな朗読を聞いてみたら「ださい」は偏見だったとわかって、いまは好きな詩人であり朗読者である方がいっぱいいます。自分で朗読することに対しても、いい意味で意気込みがなくなったというか、その場に行って読むということを淡々とやるようになりました。

他国の言葉をもっと知りたい!
淡々といえば、メデジンの詩祭には中国の詩人が五人くらいおられたんですが、その中で、おそらく私とあまり年が変わらない男性の詩がとても気になったんです。中国語はまったくわからないので、スペイン語訳の朗読に耳を傾けていたら、私でもわかるような簡単な単語がどんどん出てきて、それこそ淡々としている感じに「あれ、この人と私は書きたいものがけっこう似ているかもしれない」と思ったんですね。それで中国語が知りたくなって、スマホのアプリで中国語を勉強するようになったら、タイのバンコクで開催する中国の詩祭に呼ばれたんです。
――中国語を勉強していることを、誰に言っていたわけでもないのに?
そうなんです。そういう不思議なご縁があって……でも、微妙にズレているんですよね。実際に行くのは中国ではなく、タイで開かれる中国の詩祭なので(笑)。どうもビザの問題が関係しているらしいんですが、自分の願望が予想していない形で現実になる感じはおもしろいですね。
――今後、どんなご縁が結ばれていくかが楽しみですね。最後に、詩のイベントに参加されてきたこれまでの経験をふまえて、やってみたいと思うようになったことがあれば教えてください。
他国の言語をもっと知りたいと思うようになりました。朗読を聴くにしても、コミュニケーションするにしても、それだけは毎回、悔しい思いをしているので。
コロナ禍になって、はじめてNetflixを契約したんです。それまではドラマを観ていると仕事をする時間がなくなりそうだと思っていたんですが、ずっと自宅にいなくちゃいけないならそれもいいかと思って。そうしたら、怒濤の勢いで観てしまって、韓国ドラマはもちろん、K-POPも好きになりました。
そこからアプリで韓国語を勉強するようになったおかげで、去年の三月に韓国へ行ったときには、屋台に立ち寄って韓国語で注文できるくらいになっていたんです。海外でのイベントに通訳なども兼ねて同行してくれる夫(美術家の小林大賀氏)は英語とスペイン語ができるので、手分けしようという話になって、中国語も韓国語と同じく「私が担当だ!」という気持ちで勉強しています。
――国内を旅したり、イベントに参加してみたいという気持ちは?
かなりあります。仕事でもプライベートでも国内はけっこう巡っていて、コロナ禍で海外に行きづらいときに、国内のまだ行ったことのない場所に長期滞在して詩を書きたいと考えましたし、いまも考えています。いまのところ、四国にはまだあまりご縁がないので、行ってみたいですね。
――そう考えていると、そのうち岡山あたりでお仕事が……。
岡山とか広島とか、ちょっとズレたところでご縁が生まれるかもしれないですね(笑)。

みすみ・みづき 1981年、鹿児島県生まれ。第十回中原中也賞、第二十二回萩原朔太郎賞など、受賞多数。詩集に『週末のアルペジオ』(春陽堂書店)、『どこにでもあるケーキ』『よいひかり』(ナナロク社)、エッセイ集に『とりとめなく庭が』(ナナロク社)など、著作も多数ある。