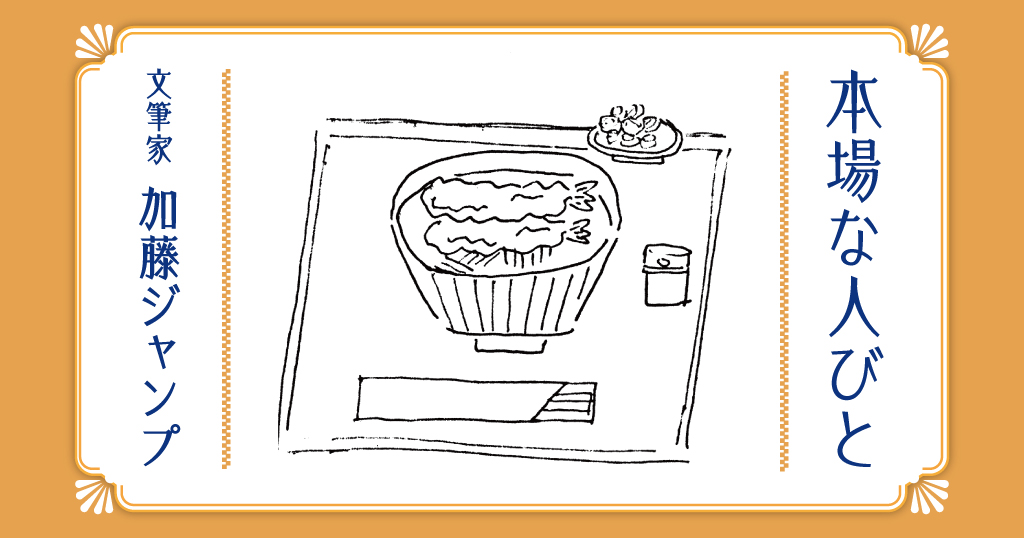第18回(番外編) メリーさんと天ぷら蕎麦
ヨコハマ映画館慕情
見た映画はとうに忘れたのに、あの白塗りの顔はおぼえている。
四十数年前のことである。いまもそうだが、私は小学生の頃からかなりの近視であった。ところが中学に入るまでメガネはかけていなかった。仮性近視の子どもが早々にメガネをかけてしまうと、どんどん近視の度が進む、という、どこで聞きかじったのか知らない亡母の論理によって、すでにそれなりに近視だったが裸眼を通していた。だからちょっと遠くを見るときはいつも目を細めていた。
長じてから居酒屋で居合わせた女性が、
「近眼のオトコが目を細めて遠くを見てるのって好き」
と宣[のたま]うのを耳にした。世の中の女性が皆こういう人になってくれたら良いと願った。
とまれ、小学生の頃の私はちょっと離れたところにあるものを見るために、年中を目を細めていたのである。
映画館に行ってもそうだった。どうしても目を細めて見てしまう。
当時は、今みたいにショッピングモールのオマケみたいに、そこらじゅうにシネコンなんてなかったから、横浜の郊外の実家から映画を見に行くといったら、電車に乗って横浜駅か関内駅へ行くのがお約束だった。横浜駅なら相鉄ムービルという映画館(今も同じ名前の映画館があるけれど、それは1988年に出来た二代目で、また建て替えるらしい)。もう二駅足を伸ばして関内駅周辺へ行くと、いろんな配給会社の映画館が何軒もあって、たいがいの映画が見られた。
相鉄ムービルはふりかえるとシネコンの走りみたいなもので、ビル一棟まるごと映画館でうまっているという当時としては珍しい施設だった。ただ、私はそういう映画館ビルよりも、ロビーにガラスケースがあって、そこでお菓子を売っていたり、電車のシートみたいな、毛足の短いビロードもどきみたいな布ばりの椅子や、暗い表情のもぎりの人とかがいる関内の映画館が好きだった。
相鉄ムービルが関内の映画館に優[まさ]っているのは、横浜駅にダンキンドーナツがあったことだった。ムービルとダンキンは獅子てんや・瀬戸わんやくらい完璧なペアだった。ダンキンドーナツはとうに日本から撤退し、今では村上春樹の文章でお目にかかれるくらいである。でも、あの頃のダンキンドーナツは、私のなかでは、「日本一アメリカンなおやつ」だった。そこだけは関内の映画館が完敗なのだった。
ただ、やっぱり映画は関内で見るのが好きだった。なにしろ関内の映画館には個性があった。
チケット売り場がかっこよかった馬車道東宝。伊勢佐木町には松竹、日活、オデヲン、日劇、東映、ピカデリー……ざっと思い出してもたくさんの映画館があって、それぞれに思い出がある。東映のロビーのリノリウムの色が好きだったし、松竹では柿の種の袋を開けた時、盛大にぶちまけて上映中大層迷惑をかけたことがあった。オデヲンのスクリーンがあまりに小さくて、帰りに別の映画館で口直ししたこともあったし、日活では映画館の一階にあった店でモデルガンを眺めていると、隣りにいたおじさんが大層詳しく説明してくれて、なぜこの人はこんなに銃にくわしいのか後になってちょっと怖くなったりした。どれも良い思い出である。
別次元の「見てはいけない」
その人を初めて見たのは伊勢佐木町だった。ただ、その人を見た日、一体、なぜ伊勢佐木町にいたのかはおぼえていない。
その頃、私が伊勢佐木町に行くとしたら映画を見るか、さもなくば有隣堂という書店(今でも好きだ)か松坂屋(食堂がいかしていた)あたりにしか用が無かった。それもたいがい誰か大人が一緒にいた。だから、その人を見た時も傍には誰か年長者がいたはずだし(いなかった可能性もある)、おそらく何か映画を見たはずなのだけれど、それがなんだったのかはっきり思い出せない。『幻魔大戦』だったのだろうか。『さよならジュピター』だったのだろうか。前者は私が大友克洋の熱狂的ファンになったきっかけで、後者については裸で空中浮遊する三浦友和と、ユーミンの主題歌くらいしか印象に残っていないが、どちらも関内で見たはずだ。
ただ、その人が夕方の伊勢佐木町をゆったりと歩いていたことは鮮明に記憶している。大きな荷物を手にしていた。白いドレスというかオーバーのようなものを着ていて、顔は白塗り、髪の毛もほぼ白髪で目のまわりはくっきりと黒くふちどっていた。近眼でもはっきりわかる、それまでの私の人生ですれ違ったことのないタイプの人だった。
ほんとうは見たくてしかたなかった。ただ、その時は目を細めてはいけない気がしたのだった。その人物に、目を細めて凝視していることを気づかれたら何かがおこるのではないかと気が気でなかったのだ。
喧嘩とかカツアゲみたいな事象は、ほとんどの場合、いわゆる不良が(当時はどこから見ても「不良でござい」というタイプの青年がたくさんいた)
「なに見てんだよ」
と、からんでくることが端緒である(といっても私は不良の人びととはあんまり縁がなかったので、こうした知識は主に漫画で学んだ)。ただ、そういう「見てはいけない」とはまったく別次元の「見てはいけない」という雰囲気が彼女から漂っていた。こういう言い方をしてはいけないのかもしれないが、当時の私は妖怪に出会ったような心持ちになっていた(そう考えると、その時見た映画は『幻魔大戦』だったような気がしてくるのだが確信はない)。
だからなおさら、その人をじっと見つめていることを気づかれてはいけないと思ったのだ。いつものように目を細めたら、凝視していることが彼女に露見してしまう。それで必死に目を細めないようにした。でも、見たかった。見たくてしかたなかった。
ちょうど松坂屋の前あたりだったと思う。
不思議だった。
彼女が通り過ぎる間、時と空気が止まったようだった。
彼女の周りは、私と同じようにじっと見てはいけないと思いつつも、横目で見てしまう人が大勢いたのだと思う。ジッと見てはいないけれど、皆、見つけるやいなや、一瞬ではあるが、足を止め手を止め息を止めて目に焼き付けていた。でも、それは本当に一瞬だった。皆、どこか日常のなかのワンシーンとして、ちょっと当たり前のようにしていた。騒がず、なんとなくやり過ごす。ちょっと、そこが、不思議だったし、なんとなく、これが社会なのかと子ども心に感心してしまった。
その後、メリーさんがどこをどう歩いて行ったのか、それも覚えていない。夕方だったけれど、メリーさんが古いデパートの前をもたもたと歩く光景は白昼夢のようだった。
それから、蕎麦を食べた。伊勢佐木町の蕎麦屋で、いつもなら天ザルなのに、その時はなぜか温かい天ぷら蕎麦を食べた。蕎麦は子どもの頃から冷たいの一辺倒なのに、その時、おそらく初めて温かいのを食べた。以来、奇妙というか想像だにしていかなった光景(といっては失礼だけれど)に出くわすと、なぜか(温かい)天ぷら蕎麦をいただきたくなるようになった。父が亡くなった時も天ぷら蕎麦を食べたくなったし、初めて買ったちゃんとしたギターを売り飛ばした時も天ぷら蕎麦が無性に恋しくなった。
家に帰ってから姉に、白塗りの女性を見たと話すと、それは「マリーさんかメリーさん」と教えてくれた。どうも、その頃、彼女の呼び名が変わりつつあったようだ。かつてはマリーさんと呼ばれていたが、1980年代になってから徐々にメリーさんに変わっていったらしい。目撃してから、私はことあるごとに両親や学校の先生にメリーさんについて聞き回った。
メリーさんは、横浜にとどまらず実は全国的に有名な人だった。白塗りに目の周りを一周する真っ黒なアイライン。白いフリルだらけのドレス。荷物を持って悠々と横浜の中心部に出没した。進駐軍を相手に商売をしていた人なのだと教わったが、その頃の私には今一つ理解ができず、はっきりと認識したのはもう少し経ってからのことだった。

なんとなく、しんみり
伊勢佐木町の森永LOVE(という当時はそこら中にあったファストフード店)によくいると教えてくれたのは、同級生でいちばん流行にも明るく事情通のI君だった。当時の僕らの間ではストライプのシャツを着ている人を見かけると「森永LOVE」と言い合って面白がることが密かに流行していた。森永LOVEの制服はちょっとパジャマみたいな太いストライプで、今思い出しても可愛くてさえていた。そんな森永LOVEにメリーさんが居ると聞いて、I君は
「森永LOVEは怖いから、今度関内で映画を見た帰りはデイリークイーンにしよう」
と言っていた。デイリークイーンはたしか元町にしかなくて、私はそのことを知っていたけれど、そこは指摘しなかったし、そもそも、映画の帰りだろうとなんだろうと、森永LOVEみたいなファストフード店に小学生だけで行ったりすることはなかった。
それ以来、何度かメリーさんを見かけた。大学時代には、何の気の迷いか伊勢佐木町にあった司法試験の予備校なんてところに通ってしまったこともあった。予備校よりも帰りに伊勢佐木町で一杯やることのほうが好きになってしまった。その帰りに彼女を見たこともあった。その頃は、手押し車みたいなものを押すようになっていた。初めて見かけてから十年以上の歳月が過ぎていたが、あまり変化を感じなかった。アンチエージングというか、ずっと過剰なエージングをしたままの彼女だった。
それよりも、当時は夕方になると黄色い小さな猿を散歩させる人がいて、そっちのほうが気になっていたくらいだった。それからしばらくして、彼女を見かけることはなくなった。伊勢佐木町あたりで消費する私の酒量もその頃から格段に増えていったので、そのせいで記憶が曖昧になってしまったのかと思ったら、そういうわけではなく、本当にその頃、彼女は横浜を去ったのだという。調べてみたら、その後は故郷にほど近い岡山県の津山の老人ホームに入りそこで死んだらしい。当たり前だけれど、彼女も人間で、亡くなったのだった。
今でも伊勢佐木町あたりで横浜の人と飲んでいると、メリーさんを思い出したり、めいめい、どんなシチュエーションで見かけたかを話したりすることがある。そういう話をすると、だいたい、ひどく盛り上がった後、なんとなくしんみりする。おそらく、メリーさんの話は、メリーさんが生きていた時代の話だからなのだろう。そもそも、メリーさんを見られた時代、あの時代だったからこそ、ああいうメリーさんでいられたのではないかと思ったりする。
今だったら少なからぬ人数の通行人が彼女にスマホを向けて写真なり動画なりを撮っただろう。彼女に失礼な質問をして怒らせたりして、動画を撮ってバズろうとするようなタチの悪いのも一人や二人ではすまなかったはずだ。前携帯電話時代だったのは、彼女にとってすこしだけ幸せなことだったのかもしれない。
私が公式に酒を吞むようになってから三十年以上の月日が過ぎていて、関内駅の近く、伊勢佐木町の様子もずいぶん変わった。酒場に限らず好きな店もずいぶんなくなった。
私が幼かった五十年前、昭和三年生まれの亡母などは「昔の伊勢佐木町はよかった」としきりに口にしていたくらいだから、このあたりはずっと変貌しつづけているのだ。ただ、変貌は、だいたい予期せぬ方向を向いている気がする。ずっと良い街だとは思うものの、変わらないでほしかったところはたくさんある。そういう街のなかで、メリーさんは、あのメリーさんとして認識されてからは、ほぼ変わることのない姿を見せていた。初めて目撃したときは怖くてしかたなかったのに、いつの間にか、
「あ、今日もメリーさん、いたなあ」
などと呑気にとらえるようになっていった。どこかで、彼女を変わらないことのシンボルみたいに考えていたのかもしれない。だからといって、再び彼女のような人が現れるのを待っているなんてことは全然ない。
ただ、今でも、松坂屋(だった場所)の前を歩いたりすると、はっきりと彼女を思い出す。あとは天ぷら蕎麦を食べるときもやっぱり思い浮かぶ。人間が伝説になるということは、こういうことなのかな、と思ったりする。
タイトルイラスト=筆者
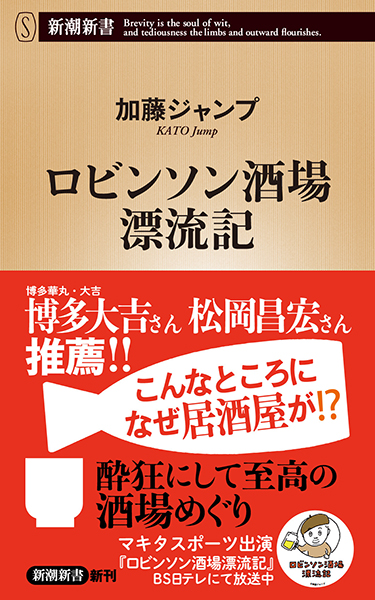
かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。最新刊に『ロビンソン酒場漂流記』(新潮新書)。