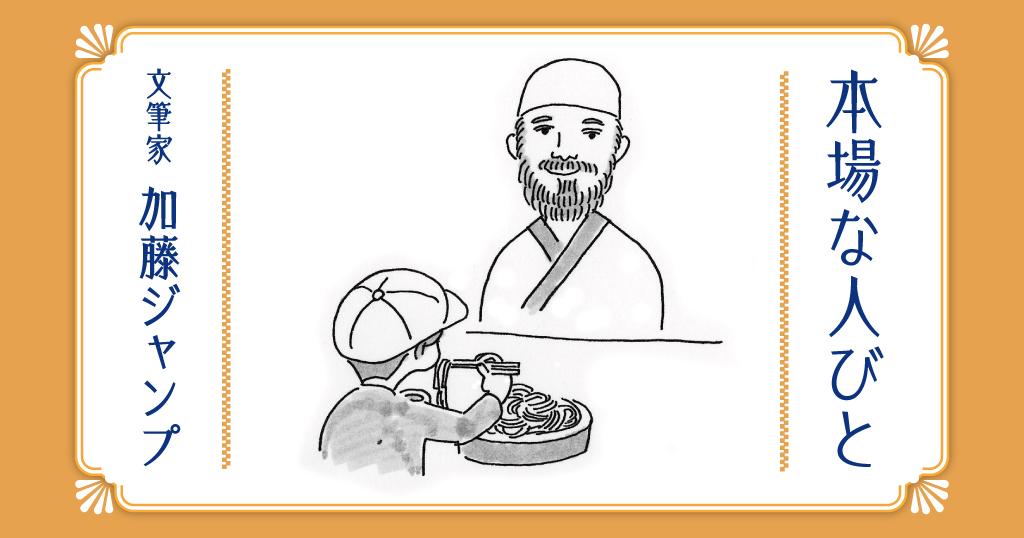第11回 蕎麦に魅せられたバングラデシュ人
新しい内閣が誕生した。集合写真を見たら、ちょっとヨレっとしている。なんとなくズボンなんかシワシワだったりするし、裾がダボっとしていたりする。撮影したカメラの人も声をかけてあげればいいのに、よほど、話しかけにくい人たちなのだろうか。目立ってヨレっとした集合写真だったが、これまでの内閣と変わったのはそのあたりくらいで、結局のところ、やることは……どうなのだろうか……。嗚呼。ニュースを目にし新聞を読むにつけ、私の酒量は増える一方である。そして、長くこの国に暮らす外国の人から見たら、いまの、この感じってどうなのだろう……マイルドやけ酒を飲みながらいつも考えている。
海外から来て、自身の本国の料理をふるまう店を営んでいる人たち、すなわち、本場な人たちに会って、その料理を食べて、どうしてわざわざ日本まで来てくれて、母国の旨いものを披露してくれるのか聞いてまわるのが、このルポの主旨である。ただ、今回は、ちょっとだけ、いささか、いつもと趣を異にしているかもしれない。
逗子で愛されつづけて、20年近い歴史を持つ店が取材先である。店を経営するのは、バングラデシュからやってきたバングラデシュ人の男性である。
「ああ、カレー系のお店なのか、今回は」
と思われる方も少なくないだろうが、今回訪れるお店は蕎麦屋さんである。バングラデシュの本場の料理ではなく、本場、日本の料理なのである。
これぞ寅次郎の気持ち
JR横須賀線の逗子駅は西口と東口でずいぶんと様相が異なっている。東側は、商店がひしめきあいバスやタクシーがロータリーをくるくると回る大きな駅だ。ところが西口はというと、いきなり道路というか、家があるばかり。商店もコンビニも郵便局も駅前には見当たらない。
逗子駅で件の西口を出てから、しまった、と思った。蕎麦屋さんに行くのに現金を全然持っていなかったのである。クレジットカードも使えるかもしれないが、個人店ではなるべく現金をつかうようにしている。
私は蕎麦っ食いで、食い意地が張っているので、旨い蕎麦屋に行くと、蕎麦前でこれでもかというほど肴を食べたえうに、もりを二枚は平気でたぐる。そういうわけで、それなりに澁澤榮一さん(別に福翁でもOKだけど)が財布に鎮座してくれないと些か不安なのである。
コンビニに行けば現金をおろせると思ったものの、駅前にはそんなものはない。東口に戻ろうと思ったら跨線橋もどこだかわからない。しかたなくスマホでコンビニを探して、てくてくと歩いた。
途中、目的の店を通り過ぎたとき、店の窓に私の姿がうつった。その、こそこそした様子を見て私は国民的映画シリーズを思い出した。『男はつらいよ』の主人公の車寅次郎は、実家の団子屋「とらや」(シリーズ途中から「くるまや」)に里帰りするとき、素知らぬふりで、店前を一旦通り過ぎることがよくあった。
後継ぎになるべき立場ながら家を飛び出して以来、香具師をしながら日本を旅してまわる男は、盆であれ暮れであれ、堂々とは帰りづらい。私には継ぐべき家業もなかったし、出奔や逐電の経験もないのだが、今回、件の店の前をそそくさと通り過ぎたとき、ちょっとだけ、寅さんと心持ちを共有できたような気がした。
コンビニで現金をおろし(こういうとき、軍資金と言いたがる人がいるけれど、私はそこそこディープな平和主義者なので言わない)、いざ向かったのは、蕎麦店「石臼そば」である。
店主の持ちビルの一階と二階が店舗になっている。一階の入り口には外からも見えるように石臼が置かれている。
「いらっしゃいませ」
ぜんぜん訛りのない日本語で迎えてくれたのは、店主のチョウドリ・エムディ・レザウル・カリムさんである。いま五十代という。豊かなヒゲを顎にたくわえキリッとした面立ちは、たしかにバングラデシュの人の雰囲気である。
メニューを見ると、もりそばからはじまって肴までいろいろ揃っている。酒もしかり。
「私は全然吞めないですけどね、お客さんから教えてもらって、美味しいのを揃えるようにしてます」
チョウドリさんの、あまりに流暢な日本語による説明を聞いていると、チョウドリさんは下戸なのかなと思ってしまいそうになったが、そうではない。チョウドリさんは、イスラム教徒なのである。だから吞めないのではなく、吞まないのだ。
メニューは完全に「本場のお蕎麦屋さん」なのだが、そのなかにいくつか、チョウドリさんの故郷との接点を感じるメニューがある。
――カレーそば、いいですね。これは、バングラ風なんですか?
「スパイスはバングラデシュで使うものを使ってますが、日本風にしあげてますよ、でも、ちょっと辛いの。人気ありますよ」
これは頼まないわけにいかない。一緒に鶏の唐揚げとスパイシーチキンというのをお願いした。

衝撃的な出会い
チョウドリさんが日本に来たのは「たしか1996年」という。バングラデシュの大学で経済学を学んでいたチョウドリさんは、
「小学校の三年生くらいだったと思うですが、広島と長崎のことを学校で教わったんですよね。学校では、投下の日には黙禱をしていました。以来、ずっと日本のことが気になっていたんですが、大学生になると、留学していた先輩が『日本っていいよ』と言ってたんですよね。それからしばらくして『来てみなよ』って誘ってくれて」
それが来日(留学)のきっかけだった。
東京の大学と日本語学校で学びはじめたチョウドリさんは、お酒は吞めないながらも居酒屋でアルバイトもはじめた。もともとバングラデシュに住んでいたころから、辛いものが苦手だったそうで、和食にもすぐに馴染めた。留学生活にもすこしずつ慣れたころ、大学の先生に連れられて小田原に研修に行くことになった。そのとき、衝撃的な出会いがあった。
先生は、学生たちに日本文化の一つとして日本食を紹介したかったのだろう。蕎麦を知っているかとチョウドリさんたちに聞いたという。もちろんチョウドリさんは、
「蕎麦なんて全然知りませんでした。先生は日本ではお年寄りも子どもも食べるもので、栄養もたっぷりで、年越しや引っ越しのときに縁起ものとして食べるといった話を聞かせてくれたんです。料理を食べながら、蕎麦か、すごいものがあるな、と聞いていたんですが、やがて、注文したもり蕎麦が運ばれてきたんです。これを食べたら……なんて旨いんだろうって。麺一本ずつはとてもシンプルな蕎麦が、つゆがからんで旨くなる……。こんなものが日本にはあるんだ、って、もう驚いてしまって……」
〈まず、バングラデシュ出身のスタッフの方が、うやうやしく運んできてくれたのは鶏の唐揚げ。こんがり狐色に揚がったそれは、ふんわりと香ばしいにおいを漂わせている。これはかぶりつかなければいけない。ガブリと嚙んだ瞬間、サクリと衣が割れる音が骨伝導した。同時に、鶏の汁気が舌を包みこむ。衣の味はきりっと塩味が効いていて、鶏の元来の出汁感のある味をひきたてている。これでビールがあれば無敵だ〉
居酒屋のアルバイトにもどっても、チョウドリさんずっと蕎麦のことを考えていたらしい。よほど旨かったのだろう。どこの蕎麦屋さんだったのか聞いたが、
「わからないんですよね、日本に来たばかりのとき、連れていってもらったところって。ついていくのが精一杯。目につくもの全てが初めてですから」
たしかにそうだ。私も大学に入って初めて先輩に連れて行かれたステーキ屋がどこだったのか、しばらくわからなかった。
小田原で蕎麦に夢中になったチョウドリさんは、それ以来寝ても覚めても蕎麦のことばかり考えていたらしい。
「図書館に行って文献を調べたりしたら、居酒屋の発祥も蕎麦屋さんだっていうじゃないですか。今みたいに、いろいろ集まれるところもなかったから、何かっていうと、集まりは蕎麦屋の二階だったというし。天ぷらとか肴にして日本酒を吞んでいた蕎麦屋さんの歴史も、これは奥深いなあ、とますます好きになったんですよね」
チャンスがあれば蕎麦屋さんでお蕎麦を食べていたというチョウドリさん。そのうちに、
――やっぱり自分で打ちたくなりますよね?
「そうなんですよ。いてもたってもいられなくなってしまって。出向いたお蕎麦屋さんやアルバイト先の料理長さんとか、いろんな人に『自分で蕎麦が打ちたい』って言ったんですが、みんな『無理、無理』とか『日本人でもできないんだから無理だよ』って言うんですよね」
――外国人のお蕎麦屋さんを見たことが無かったんでしょうねえ。とりあえず無理って言ってしまう
「でも、みんなに無理だと言われたら、逆に燃えてきちゃって。絶対、やってやるって。外国人には無理っていうなら、よーし、チャレンジするよ、私が、って(笑)」
――でも、国籍とか関係無く、それだけの情熱があったら相手も変わってきそうですよね
「そのうちに、私の働きぶりを見てた人は、チョウドリさんならできるかもしれないよ、と言ってくれるようになったんですよね。『まずはお蕎麦屋さんで働いてみたらいいんじゃない』と、言うので、何軒も蕎麦屋をまわったんですが、門前払いでした」
半年で免許皆伝
〈つぎにやってきたのがスパイシーチキン。最盛期の柿のような朱色に近い刺激的な色の衣をまとった見た目に、辛いものが好きな人間には見るだけで口中が困るほど潤ってくる。衣には細く丸みをおびた突起があり、ガブリと齧ったとき、それがホロホロと崩れる。散らばる衣についたスパイスは、はじめパッと火花のように辛かったと思うと、後からじわりと辛味とともに香りが鼻の奥まで広がる。鶏はサクサクと崩れ汁気が衣の刺激と混ざりあう。口中の国際交流。ピリッとした辛味が持続するなか、次から次に口へと放り込んでしまう。旨い〉
――スパイシーチキン旨いですねえ
「ああ、ほんとに? よかったあ」
――これはバングラにも似たものがあったりするんですか?
「いや、これは、やっぱりスパイスだけバングラと同じものも使っているけど、あくまでお蕎麦屋さんの一品料理ですね」
たしかにスパイシーだけれど、異国情緒はあまり感じないし、お酒の味を消してしまうようなところはなくて、蕎麦前として楽しめる味なのだ。チョウドリさん、根っから日本蕎麦屋さんなのである。

文献を調べ、蕎麦を食べ歩き、自分で蕎麦を打ちたいという情熱に突き動かされ、お蕎麦屋さんで働きたいと申し込んでも肘鉄砲を食らっていたチョウドリさん。「だったら」と、発想を変えた。柔軟なのである。
「蕎麦屋さんで働けないなら、自分で蕎麦屋さんを開けばいいんだ、って」
こういうことを考える人はいる。ただ、チョウドリさんはこれを迷わず実行し、成し遂げてしまったのである。
蕎麦屋を開くにあたって、チョウドリさんは、まず、
「蕎麦の実から研究することにしたんです。お蕎麦屋さんで断られたから、今度は製麺所を回って見学を申し込みました。電話でアポをとろうと思っても断られる可能性が高い。だから、いきなり製麺工場まで行って見学させてください、と申し込んでみたんです。でも、やっぱり何軒も断られまして」
ただ、チョウドリさんはへこたれなかった。とうとう製麺所の見学がかなったのである。しかも場所は小田原。チョウドリさんが蕎麦に目覚めた街と同じだった。
「久津間製麺所という会社に行ったところ、会長さんが受け入れてくれたんです。工場長を呼んで『こいつに見せてやって』と」
――度量の大きい会長さんだったんですねえ
「実際に身長も2メートル近くあるような大きな人なんです(笑)」
ついに蕎麦打ちの現場を見たチョウドリさん。
「石臼がズラッと並んでいる景色は、それはすごいものでした」
その時、工場の奥で蕎麦打ちをしている何人かの人が見えた。工場の壁には張り紙があって、蕎麦打ちの研修を実施していることが書かれていた。
今がチャンス――。
チョウドリさんは、いきなり会長さんの元へ行き尋ねた。
「私にも蕎麦打ちの修行をさせてくださいと言ったんです。すると、会長は『やるの? できるの?』と二言三言聞いただけで、傍にいた工場長に『こいつ、仕込んでやって』って言ってくれて」
こうして、とうとうチョウドリさんは蕎麦打ちを教わることになった。
――どうして会長さんは、OKを出されたんでしょうね
「直接じゃないんですけど、人に話しているところを聞いちゃったんですが、『あいつ、オレの目をじっと見つめて話すんだよ。ありゃあ、本気だって思った』って言ってました」
――僕も目を見て話すようにしますね……で、どのくらい修行の期間はあったんですか?
「やるからには全力で集中して短期間で全部覚えてやるんだ、って。半年くらいで、『もうやれるよ』と言われるまでになりました」
――半年って、すごいですよ、それは。
「わたしはね、修行は時間じゃないと思ってるんですよ。資格とかもそう。店を開いてから、調理師免許を持ってるのに、ロクにネギも切れないような人に会ったこともあります。やれるかやれないかは、時間とか資格じゃない。気持ちが大事」
製麺所での蕎麦打ち修行は免許皆伝。その後、つゆの味についてもお墨付きを得た(勤めていた某社社員食堂のシェフがうなずいたというが、そのシェフが実は皇室晩餐会でも料理を振る舞うような人だったことは後に知ったという)。あとは場所を探して店を開くとなったとき、チョウドリさんの頭には逗子という土地があった。
「職場も学校も東京だったんですけど、友だちが逗子に住んでいて、行くたびに海や山があって空気が綺麗だったから、やるならここだ、と思ってたんです」
2004年、ついに念願の店を持った。店名は「石臼そば」。今の店とはちがって駅から離れた住宅街のなかにあった。それまでに二軒の店が潰れたいわくつきの物件で、周りからは反対された。でもチョウドリさんは自信があった。
「旨い蕎麦を出せば、かならず流行る、と思ってました」
〈修行半年と聞くと最初は驚くけれど、チョウドリさんの蕎麦を口にしたら、いや、もう天晴れ、と誰もが思うだろう。なにしろ旨い。たぐったときの感触のよさ。舌先で、ふわっと香ばしく清々しい蕎麦の香りがただようと思ったら、喉をさっと駆け抜けていく。清涼感の奥底にコクがあって、蕎麦っていいよなあ、と再認識する。この日はカレー蕎麦と、いささか異色のメニューだったけれど、カレーの、バングラデシュ的な香辛料の香りと刺激的な辛味が、この店のかえしと上手くマッチしている。だが、このエスニックにして完全に和な汁は、蕎麦にからんだとき、決して蕎麦の香りを邪魔しない。さりとて強力な、本格的なカレーの香りもしっかりと楽しめる。ただ、チョウドリさんの蕎麦はその強い汁に負けず、むしろ、汁と絡みあうことで、ことさら、蕎麦らしさを際立たせて口中を過ぎていく。こりゃあ旨い〉
人生に必要なものってなに?
これだけ旨い蕎麦だから、多少不便な場所だったとしても初めから上手くいったのではないかと思ったが、問題はそこではなかった。
「店を開けると、私が顔を出すでしょ。そうすると『え? ここお蕎麦屋さんだよね?』ってお客さんが戸惑うんですよ。そうですよ、と答えても、また来ますって、帰っちゃう人が大勢いました」
そんな状況が一年近くつづいた。誰も客が来ない日もあった。だが、
「店に入っちゃったから、せっかくだから食べてみるか、って実際に食べてくれた人が、旨いって納得してくれたんでしょうね」
口コミは瞬く間に広まり、ほどなくして行列、完売の店になった。しばらくして店を引っ越し、それまでは粉の状態で仕入れていたのを、蕎麦の実を仕入れ店で引くようになり、完全に「三たて(旨い蕎麦の三つの要件としてよく言われる、引きたて、打ちたて、茹でたての三つを称して言う)」を実現した。今の場所(といっても建物は違って、かなり変わった形をした物件だった)に移っても店は絶好調。逗子の旨い蕎麦屋としてどんどん評判は広がっていった。
しばらくして横浜の中心部、JR関内駅近くの蕎麦屋から助けてほしいと声がかかった。チョウドリさんは逗子の店を弟子に託し、関内の店を切り盛りしたところ、わずか二週間で行列ができる店に生まれ変わらせてしまった。ただ、
「逗子の店の評判が下がってしまって。そこに東日本大震災が起こったんですよね。震災の日は、お店のお客さんのなかに逗子の人がいて一緒に歩いて帰りました。時間をかけて歩いて帰りながらいろんなことを考えました。それで、私は、行くところにある蕎麦屋じゃなくて、帰ったところにある蕎麦屋がいい、って思ったんです」
そうしてチョウドリさんは逗子に戻ることに決めた。ただ、今度はしっかりと使いやすい建物にしたい。そこで、今の店の土地建物を買って新いビルを建てようときめた。
――でも、外国の人が銀行でお金を借りようと思うと、そりゃあ大変なんじゃないですか?
「そうなんですよ。でもね、関内の店のころ、金融機関に勤めている常連さんの方もいて、『チョウドリさんなら安心してお貸しできます』って」
――いい話だ……。
「いや、もうほんとうに人に恵まれてて。でもね、私、うちの店でスタッフを募集するときいつも聞くんですよ。人生に必要なものってなに?って」
――そんな難しい質問みんな答えられないんじゃないですか? 僕なんか五十年それを探してますよ。
「(笑)。いやでもね、私は思うんですよ。人間、着るもの、食べるもの、寝るところ、その三つがあれば、あとの贅沢はいらないでしょって」
――でも、チョウドリさん、ちゃんとビルまで建てて。
「そう、夢がかなったんで、つぎはなにをしようかな、なんて思うんです。こないだ、ようやく運転免許をとったんですけど、最近、長距離のトラックドライバーを見てるとかっこういいなあ、って思っちゃって」
――まさか……。
「教習所の先生もお店に来てくれるんで、『大型トラックの免許ってどうやってとるんですか?』って聞いたら『また、またあ』って(笑)。でも、チョウドリさんならとれますよ、って言ってました(笑)
――そしたら、大型移動蕎麦屋トラックってのはどうですか?
「それは、しないかなあ(笑)」

その日も、チョウドリさんの店には、元スタッフだという日本人女性が二人でやって来ていた。
「彼女たち、CAになったんだけど、実家に帰省するときは家に帰る前にうちの店に寄ってくれるんですよ。悩み事はすぐに連絡してくるし、私もそれには精一杯こたえてるんだけど。まあ、この店が帰れる場所になっているって、なかなかいいなあと思うんですよね」
海外から来て、本場日本で蕎麦屋を切り盛りする。それだけで大変なことに思えるけれど、チョウドリさんは、情熱と才能でそれをかなえた。そして、その街に住む人、ルーツを持つ人たちに「居場所」を提供している。こういう本場な人が増えたら、ますます、この国の食、のみならずアレもコレもずっと豊かになる気がする。
タイトル、本文内イラスト=筆者

かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。